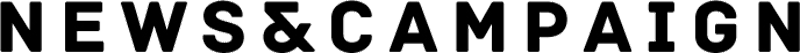ニュースやお得なキャンペーンをご紹介しています。
2026.02.12 / 更新日:2026/02/12
【呼吸の浅さ=疲労の蓄積】
こんばんは!
YAMATO355の葛原です^^
「なんかずっと疲れている気がする」
「寝てもスッキリしない」
「肩や首がいつも張っている」
そんな人、多くないでしょうか?
実はそれ、“体力不足”ではなく
呼吸の浅さが関係しているかもしれません👈
・呼吸と自律神経のつながり
僕たちの身体は、自律神経というシステムによって常にコントロールされています。
自律神経には2種類あります↓
①交感神経(アクセル)
②副交感神経(ブレーキ)
仕事をするときや緊張するとき、運動するときは交感神経🔥
休むときやリラックスするとき、眠るときは副交感神経🧊
このバランスが整っていることが、
「疲れにくい身体」の条件です!
そしてこの自律神経に、最もダイレクトに影響を与えるのが〝呼吸〟です。
・呼吸が浅いと、身体は“戦闘モード”になる
呼吸が浅い人の多くは胸だけで呼吸をしています!
肩が少し上下するような、速くて短い呼吸です。
この呼吸パターンは、身体に
「何かに備えろ」というサインを出します!
つまり、常に軽い“戦闘モード”で、交感神経が優位になりやすくなります
その結果、
・疲れが抜けにくい
・寝つきが悪い
・肩こり・首こりが慢性化する
・気持ちに余裕がなくなる
・甘いものや刺激を求めやすくなる
といったマイナスな状態が起こりやすくなります❌
頑張っているのに、回復しない。
その原因が「呼吸」だった、というケースは少なくありません。
・なぜ現代人は呼吸が浅いのか?
理由はシンプルです。
・デスクワーク
・スマホ姿勢
・ストレス過多
・運動不足
前かがみの姿勢が続くと、胸郭(胸まわり)が固まります。
すると本来メインで使われるはずの「横隔膜」がうまく働かず、代わりに首や肩の筋肉が頑張るようになります。
これが、肩こりと浅い呼吸の正体❌
姿勢と呼吸と自律神経は、
実は全部つながっています!
・呼吸が整うと、何が変わるのか?
呼吸がゆっくり深くなると、副交感神経が働きやすくなります。
すると、
・心拍が安定する
・血流がよくなる
・睡眠の質が上がる
・回復力が上がる
そしてもう一つ。
見た目が変わります🔥
呼吸が整うと、自然に胸が開きます。
力みが抜け、表情も柔らかくなります。
姿勢が変わると、印象が変わる。
身体づくりは、筋肉だけの話ではありません。
「どう呼吸しているか」も、確実に影響します。
トレーニングも、食事も大切です。
でも、常に身体が力んでいる状態ではその効果は最大化しません。
呼吸は、お金もかからず、道具もいらず、今日から変えられる習慣です。
もし最近、なんとなく疲れやすいと感じているなら、一度、自分の呼吸に意識を向けてみてください。
身体を整える最初の一歩は、
意外とシンプルなところにあります^^
2026.01.29 / 更新日:2026/01/29
【モノクロ】
こんばんは!
YAMATO355の葛原です^^
最近、仕事以外の時間はiPhoneの画面をモノクロ(白黒)表示にして使っておりまして🕶️
目的はシンプルで、
・SNSを無意識に開かない
・手頃なドーパミン摂取を減らす
・なんとなくスクロールをやめる
の3点!!!
結果から言うと、
スマホを眺める時間は体感ではかなり減りました^^
なぜモノクロにすると、スマホを触らなくなるのか?
👉色はそれだけで“報酬”になっているからです!
SNSやアプリは鮮やかな写真、赤い通知バッジ、目を引くサムネイルなどなど、こうした色彩刺激を使って、脳の「注意」や「期待感」を引き出すように設計されています!
モノクロにすると、情報の魅力が一気に落ち、開きたい理由が減ることで、行動にワンクッション入ります!
結果、無意識のスクロールが起きにくくなるといった感じです⭕️
実際、大規模研究はまだ少ないものの、小規模な実験や観察データではこんな傾向が報告されています!
・1日あたり20〜40分ほどスマホ利用時間が減少
・週換算で 約2〜3時間の削減
・一部では 最大40%程度減ったという報告も👀
重要なのは、「我慢して減らした」ではなく〝自然と触らなくなった〟という点。
これが継続しやすい理由でもあります。
ドーパミンを“出さない”というより
出やすい環境を遠ざけている
と考えるのが近く、デジタルデトックスというより「刺激の最適化」という感覚ですね⭕️
「SNSをやめる」ではなく
「距離をちょうど良くする」方法として、かなり現実的な手法です!
正直、自分も
「もっと早くやっておけば良かった」
と思うくらいには効果を感じていますし、時間の浪費に悩む方には本当におすすめですので、ぜひ試してみてくださいね👍
2026.01.22 / 更新日:2026/01/22
【カフェイン】
こんにちは!
YAMATO355の葛原です^^
朝の一杯や仕事中のコーヒーブレイクなど、カフェインは眠気を覚まし、やる気や集中力を高める心強い味方です!
自分も仕事の合間や、勉強中などに嗜むことが多いです^^
カフェインを飲むと中枢神経が刺激され、交感神経優位の状態になり、下記の様な物質が分泌されます👀
1、アドレナリン・ノルアドレナリン
→ 心拍数・血圧上昇、血糖値上昇、瞬発的な集中力UP
2、ドーパミン
→ やる気・快感の増大(モチベーションブースト)
3、エンドルフィン
→ 軽い多幸感や疲労感軽減
4、コルチゾール(ストレスホルモン)
→ 短期的にはエネルギー動員に役立つが、長期的には脂肪蓄積や筋分解のリスク❌
などなど、
脳内のアデノシン受容体をブロックすることで眠気を抑え、合わせて〝興奮物質〟が分泌させるため、気分の高揚・集中力UP・作業効率の向上が期待されるというわけですね👈
•過剰摂取の落とし穴
交感神経優位は短時間であればプラスですが、過剰・長時間続くと次のようなデメリットが生じます❌
1、副交感神経が働きにくくなる
→ 消化吸収や筋肉の回復が遅れる
2、睡眠の質低下
→ 深い睡眠が減り、成長ホルモン分泌が減少
3、コルチゾール高止まり
→ インスリン感受性低下、内臓脂肪蓄積、筋肉分解促進
4、水分不足
→ 軽い利尿作用により慢性脱水のリスク
これらのリスクを避ける為にはどれくらいが安全な量なのか??
健康な成人の場合、カフェインの安全摂取目安は1日あたり最大400mgだと言われており、例にすると
•コメダ珈琲ブレンド:約135mg/杯 → 約3杯まで
•スタバ ドリップコーヒー(トール):約235mg/杯 → 約1.5杯まで
※特に午後以降の摂取は睡眠に直結するため、午前中にまとめるのがお勧めです!
•上手に付き合うための工夫
1、午前中だけカフェインOKルールを設ける
2、デカフェやハーブティーに置き換える
3、コーヒーと同時に水をしっかり摂る(1日1.5〜2L)
4、週に1〜2日はカフェインレスデーを作る
カフェインは使い方次第で、仕事や運動のパフォーマンスを底上げしてくれる優秀なサポーターです🔥
しかし、過剰になれば交感神経優位が長引き、回復や代謝にブレーキがかかります。
「美味しいから」「習慣だから」と無意識に飲むのではなく、タイミングと量をコントロールすることが、健康的なボディメイクと高いパフォーマンス維持のカギです^^
1日に何杯も飲んでしまう、、
飲まないとやってられない、、
そんな方は自身の摂取量の見直しと、少しの節制で生活の質がグッと変わるかもしれません!
ぜひ意識してみてくださいね^^
2026.01.15 / 更新日:2026/01/15
【作業興奮】
こんばんは!
YAMATO355の葛原です^^
本を読もうと決めてたのに、結局読めずに寝てしまった、、
〇時にジムに行こうと意気込んでたのに、結局行けなかった、、
こういった経験、誰しもが一度は経験があると思います👈
そんな方に向けて、シンプルかつ超強力な方法があります!
それが〝作業興奮〟です‼️
これは「やる気が出てから動く」のではなく、動き始めることでやる気が後から出てくる現象のことを言います!
脳内では、行動を始めることでドーパミン(報酬系)が分泌され、集中力・意欲・継続力が高まるとされています!
つまり、
やる気は“準備”ではなく“結果”です。
多くの人がやりがちなのが、
・やる気が出たらやろう
・時間ができたら始めよう
・気分が乗らないから今日はやめよう
でも実際は、
やる気が出ないから始められないのではなく、始めないからやる気が出ないわけです。
ここをひっくり返せるのが作業興奮‼️
そんな作業興奮の具体的な活用方法👈
ポイントは「小さすぎるスタート」
脳は「始める瞬間」に最もエネルギーを使います。
だから最初のハードルは極限まで下げる!これ大事です!
例① 運動が続かない人
❌「30分筋トレしよう」
⭕「ウェアに着替えるだけ」
→ 5分動けたら大成功
例② 勉強・仕事を先延ばしする人
❌「1時間集中」
⭕「タイマーを5分だけセット」
→ 気づいたら20分経ってることも多い
例③ SNS発信・ブログが止まる人
❌「1記事完成させる」
⭕「タイトルだけ考える」
⭕「1行だけ書く」
などなど、面白いくらいに上手くいきますこれが!
そして重要なのは、長くやることではなく“始める回数”を増やすことです!
作業興奮を最大化するコツとして、下記のような事がよく挙げられます!
・「◯分だけ」と時間を区切る
・終わったら必ず自分を褒める
・できなかった日は責めない(仕組みを疑う)
昨日までのやろうやろうで出来なかった自分から、少しずつ脱却しましょう🔥
やる気は初めてからついてくるものです🔥
2026.01.08 / 更新日:2026/01/08
【湯船に浸かる】
こんばんは!
YAMATO355の葛原です^^
最近、とびきり寒い日が続きますね、、
暑がりでもあり、寒がりでもある葛原にはとても厳しい気温です。
日中の寒さや疲労等々で身体がガチガチになりがちですが、最近ある一つの事をルーティンに組み込んでから、かなり身体の調子が良いです!
それは何かと聞かれますと、、
今更過ぎると思いますが、入浴です🛀
自宅で湯船に湯を張るのも良いのですが、最近は近所の銭湯に行くことにハマっております(週1くらい)
昔ながらの銭湯ならではのあの空気感や、変わらないシステムが妙にしっくり来ております!!
お湯に浸かるって、漠然とした気持ち良かった〜で終わりがちですが、自律神経&血流&ホルモンまでしっかりとリカバリーしてくれるが故のあの効果👈
浸かろう!と思い立った時はお湯を沸かしていましたが、基本的にずっとシャワーで済ませていた今までの自分を本当に恨みますね^^
毎日浸かってる!なんて方も少なく無いとは思いますが、たまには自宅を飛び出し、スーパー銭湯なんかに行ってゆっくりまったり入浴するのもとてもオススメかと思います!
なかなか疲労が抜けない、、なんて方は騙されたと思って是非!
2026.01.01 / 更新日:2026/01/01
【2026年】
こんばんは!
YAMATO355の葛原です^^
皆様、新年明けましておめでとうございます㊗️
昨年は大変お世話になりました!!!
お客様、周りの方々、今の環境があっての今の自分だと改めて思っております!
そんな葛原の一年ですが、
達成できた目標もあれば出来なかった目標もありました。
昨年は、一昨年の自分に比べると成長出来たと感じる部分も多くありましたが、まだまだ×2、未熟の極みといったところだなぁ、、と感じております。
何よりもそんな自分の未熟さを指摘頂ける、気づかせて頂ける今の環境に感謝の一言です。
今季は人としてもトレーナーとしてもさらに成長出来るよう日々精進します🔥
今期のテーマは〝初志貫徹〟
己に負けないよう、頑張ります!!!
皆様、本年もよろしくお願いいたします!
2025.12.19 / 更新日:2025/12/19
【脳を鍛えるには運動を!】
こんにちは!
YAMATO355の葛原です^^
今回は「運動することの価値」について、少し違う視点から簡単にお話ししたいと思います!
運動と聞くと「ダイエット」や「筋トレ」を思い浮かべる方も多いと思いますが、脳の働きやメンタル面にもとても良い影響を与えるんです⭕️
運動が“脳”に効くという事実
自分が過去に読んだ書籍『スマホ脳』や『最高の勉強法』では、運動の脳科学的なメリットがエビデンスベースで紹介されています👈
特に注目すべきは、有酸素運動を継続することで海馬(記憶を司る脳部位)が大きくなり、集中力や思考力が向上し、ストレスへの耐性が強くなる。ということです!
なんかもうこの時点でメリットしか無さそうな雰囲気ありますよね^^
これらは単に気分の問題ではなく、実際に脳の構造や神経伝達物質に非常に良い変化が起きてるんです!
それこそ、『最高の勉強法』の著者でもありハーバード大学の教授でもあるJ・レイティさんは「運動は脳にとって“奇跡の薬”」と断言しています!
実際に運動直後の脳は「学習ゴールデンタイム」といい、
ドーパミンやノルアドレナリンといった神経伝達物質が最適化され、記憶力の定着や集中力が最大化される状態になります👈
そして気になる運動の頻度や量ですが
科学的に推奨されている運動量は以下のとおりです👇
・中強度の運動(少し息が上がる程度):週150分以上
・高強度の運動(息がかなり上がる):週120分以上
脳が喜ぶ運動の具体例としては
・朝のジョギング(20〜30分)
・勉強や仕事前のブリスクウォーク(15〜20分)
・ストレスが溜まった時の軽いラン or 森林ウォーキング
など、自分のライフスタイルに合わせて調整可能です⭕️
運動は「一番身近な自己投資」
現代はスマホや情報過多によって、脳が疲れやすく、集中力も落ちがちです。
そんな時こそ、運動がリセットボタンになります!
「賢くなりたいなら、まずは身体を動かそう」
「集中力が切れたら、まずは5分だけでも散歩を」
これが脳科学のエビデンスで裏打ちされた、最強の習慣です👈
とはいえ習慣がするのが1番ハードルが高かったりします、、
まずは週に1回、30分のウォーキングと言わず、まず最初は5分から!
気張らずに取り組んでいきましょう^^
2025.12.11 / 更新日:2025/12/11
【朝の有酸素が1日を変える?】
こんばんは!
YAMATO355の葛原です^^
「朝活をしろ!」という話ではありません!
ただ、朝に5〜10分だけ身体を動かすだけで生活の質が上がる!そんなシンプルな話です👏
・朝に動くメリット
① 体内時計が整う
朝の光+軽い運動で交感神経が自然にオンになり、頭がスッキリして1日のスタートが軽くなると言われています!
② 集中力と気分が上がる
有酸素運動は脳の血流を増やし、ドーパミンやセロトニンが分泌されやすくなります。
結果、やる気・集中力・前向きさが底上げされます⭕️
③ 代謝の流れが良くなる
朝に動くとその日1日の活動量が自然と増え、無理なく消費カロリーが積み上がる。
これが体づくりにも効いてきます!
④ メンタルが安定する
「朝に少し動けた」という行動の成功体験は、
その日1日のメンタルにも良い影響を与えます🙆
・何をすればいい?
・早歩き5〜10分
・階段をゆっくり登る
・エアロバイクを軽く回す
・その場で足踏み+簡単なストレッチ
どれも“息が上がらないレベル”でOK。
・まとめ
朝に少し身体を動かすだけで、
身体・頭・気分すべてのコンディションが整いやすくなります!
忙しい人ほどおすすめできる、小さな習慣です⭕️
2025.12.04 / 更新日:2025/12/04
【ウエストを引き締めたい】
こんばんは^^
YAMATO355の葛原です!
少し前に、お客様からの「先生たるもの、シュッとしまったウエストに、腹筋ぐらい割ってみてくださいよ!」なんて言われたのがきっかけで、今回ウエスト周りの引き締めについて自分なりに考えてみました。
自分自身、昔から胴回りは寸胴な方でして、現役サッカー部時代や数年前のコンテスト出場の際も、痩せてはいたけどウエスト周りが締まっているか?くびれているか?でいうとなんとも言えない部分ではありました❌
なんでなのか?の原因や要因は人それぞれ
1〜10まで話すとキリがないのですし、大雑把な枠組みで話をするとなると、自分の場合はまず呼吸と歩行の改善に加え、回旋系のエクササイズを取り入れるのが良いのでは?という考えに至りました、、
まずそもそも、肋骨が若干開いておりますね
横隔膜の動きは肋骨の形状に依存するので、まずここが整っていないと問題が起こるのは必然。
加えて、腹横筋や内腹斜、外腹斜に十分な出力がない。
→骨盤のポジションにも影響が出るし、さらにその骨盤に密接な股関節周りにも影響は出ますよね、、
と、ここまでが簡単な自己分析なんですが
日頃からお客様に「このストレッチは〇〇で〜」「この運動を習慣化すればお腹周りは〇〇で〜」なんて言ってる場合じゃないです^^
いろんな可能性を考えながら、いろんな情報を踏まえながら、理想のウエストをGETして見せます!乞うご期待!
2025.11.27 / 更新日:2025/11/27
【魅力を磨くには?】
こんばんは!
YAMATO355の葛原です^^
最近よく耳にする〝メンズコーチ〟というワード💪
SNSなどでもマインド・習慣・非言語コミュニケーション(ノンバーバル)など、男としての魅力を高める考え方が広がっています!
その中でほぼ全員が強調するのが “筋トレ”
筋トレには「男を魅力的に見せる要素」が詰まっています👈
■ 男が筋トレで魅力的に見える理由
① 本能的に“強さ=魅力”と判断される
姿勢の良さ・肩幅・立ち姿などは、無意識に「健康」「頼れる」「守ってくれそう」
と評価されやすい。
筋トレはこの“非言語の魅力”を最速で高めます。
② テストステロンが安定して高まる
テストステロンは
・自信
・積極性
・集中力
・性的魅力
を左右するホルモンです🔥
筋トレはこれを自然に底上げする「最強の行動」です!
③ 自己肯定感が上がり、悪習慣が勝手に減る
重さが伸びる、身体が変わる、姿勢が良くなる〜など、これらの“目に見える成功体験”が、自己効力感(=やればできる感)を高めます。
そんな成功体験の積み重ねで、睡眠や食事などの生活習慣が自然と整います。
■ 再現性が高い「習慣化すべき行動」5つ
1、週2〜3回の筋トレ(45分)
スクワット・ヒンジ・プッシュの基本だけでOK。
2、1日5分の胸郭ストレッチ&呼吸
ノンバーバルの“落ち着き”を作る最速ルート。
3、10分の姿勢リセットウォーク
歩き方が変わるだけで印象は激変。
4、寝る前15分のスマホ断ち
テストステロンと睡眠の質に直結。
5、“小さく始める→自分を褒める”
習慣超大全式の最強メソッド。
■ 筋トレは「魅力を作る土台」
筋トレは
・見た目
・立ち居振る舞い
・ホルモン
・メンタル
・生活習慣
これらを一気に改善する“男磨きの基盤”
科学的な根拠もあるからこそ、メンズコーチングの発信者が声を揃えて「まず筋トレをしろ」と言うわけです!
2025.11.21 / 更新日:2025/11/21
【メラトニン】
こんにちは!
YAMATO355の葛原です!
「寝つきが悪い、、」「睡眠の質が悪い、、」なんて悩みを抱えてる方にとって〝メラトニン〟は睡眠改善の一つの鍵になるかも知れません👀
今回はそんな〝メラトニン〟の働きや摂取することでのメリットをご紹介していきます!!
・そもそもメラトニンとは?
脳の松果体という部分から分泌されるホルモンで、体内時計の調整に深く関わってます!
暗くなると分泌が増え、体温や血圧を下げる事で体を眠りやすい状態へと導いてくれるのがこいつの役目ですね^^
そしてメラトニンの主な働きとしては
1、入眠のサポート
2、体内時計の調整
3、抗酸化作用
4、免疫サポート
等がよく挙げられます☝️
・摂取するメリット
寝つきが良くなる
深い睡眠を維持しやすくなる
自然なアプローチな為、依存性が無い
・摂取する時の注意点
適切なタイミングで摂取しないと逆に体内時計が乱れる可能性があります
翌朝まで眠気が残る事があるので、摂りすぎは注意です
長期的な服用の安全性はまだ不透明(1〜2週間の短期利用が一般的です)
そして摂取タイミングですが、
寝る30分〜1時間の服用がおすすめ⭕️
自分もたまーに飲んでから寝ますが、個人的にはスッと寝れて寝起きもスッキリって感じはあります^^
ただ、これは睡眠薬では無く「眠りやすい状態を整えるホルモン」なので、上記の注意点にも挙げたよう、これを摂り続けるのはあまり良しとされません❌
もちろん、睡眠改善においてとても有用な手段だとは思いますが、
朝はしっかりと朝日を浴びてセロトニンを活性化させる!就寝前にスマホやテレビなどの利用を減らす!
遅い時間のカフェインやアルコールの摂取は控えて、しっかりと体をオフモードに入れてからの入眠!
といった、寝る前の生活習慣が整うに越したことは無いです!
睡眠が変われば、体や脳のコンディションも大きく変わります。
鍛える&働かせるばかりでは無く、しっかりと休息もとってあげて下さいね^^
2025.11.14 / 更新日:2025/11/14
【カフェイン】
こんにちは!
YAMATO355の葛原です^^
朝の一杯や仕事中のコーヒーブレイクなど、カフェインは眠気を覚まし、やる気や集中力を高める心強い味方です!
自分も仕事の合間や、勉強中などに嗜むことが多いです^^
カフェインを飲むと中枢神経が刺激され、交感神経優位の状態になり、下記の様な物質が分泌されます👀
1、アドレナリン・ノルアドレナリン
→ 心拍数・血圧上昇、血糖値上昇、瞬発的な集中力UP
2、ドーパミン
→ やる気・快感の増大(モチベーションブースト)
3、エンドルフィン
→ 軽い多幸感や疲労感軽減
4、コルチゾール(ストレスホルモン)
→ 短期的にはエネルギー動員に役立つが、長期的には脂肪蓄積や筋分解のリスク❌
などなど、
脳内のアデノシン受容体をブロックすることで眠気を抑え、合わせて〝興奮物質〟が分泌させるため、気分の高揚・集中力UP・作業効率の向上が期待されるというわけですね👈
•過剰摂取の落とし穴
交感神経優位は短時間であればプラスですが、過剰・長時間続くと次のようなデメリットが生じます❌
1、副交感神経が働きにくくなる
→ 消化吸収や筋肉の回復が遅れる
2、睡眠の質低下
→ 深い睡眠が減り、成長ホルモン分泌が減少
3、コルチゾール高止まり
→ インスリン感受性低下、内臓脂肪蓄積、筋肉分解促進
4、水分不足
→ 軽い利尿作用により慢性脱水のリスク
これらのリスクを避ける為にはどれくらいが安全な量なのか??
健康な成人の場合、カフェインの安全摂取目安は1日あたり最大400mgだと言われており、例にすると
•コメダ珈琲ブレンド:約135mg/杯 → 約3杯まで
•スタバ ドリップコーヒー(トール):約235mg/杯 → 約1.5杯まで
※特に午後以降の摂取は睡眠に直結するため、午前中にまとめるのがお勧めです!
•上手に付き合うための工夫
1、午前中だけカフェインOKルールを設ける
2、デカフェやハーブティーに置き換える
3、コーヒーと同時に水をしっかり摂る(1日1.5〜2L)
4、週に1〜2日はカフェインレスデーを作る
カフェインは摂り方次第で、仕事や運動のパフォーマンスを底上げしてくれる優秀なサポーターです🔥
しかし、過剰になれば交感神経優位が長引き、回復や代謝にブレーキがかかります。
「美味しいから」「習慣だから」と無意識に飲むのではなく、タイミングと量をコントロールすることが、健康的なボディメイクと高いパフォーマンス維持のカギです^^
1日に何杯も飲んでしまう、、
飲まないとやってられない、、
そんな方は自身の摂取量の見直しと、少しの節制で生活の質がグッと変わるかもしれません!
ぜひ意識してみてくださいね^^